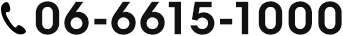聴講セミナー
2026年02月16日(月) 15:00-17:00
フィジカルAIのビジネス活用最前線
いま、AI技術は新しいステージへと進化しています。それが、物理的な世界で実際に動き、働く「フィジカルAI」です。
これまでのAIは、主にデータ分析や言語処理といった情報空間での活躍が中心でした。しかしフィジカルAIは、センサーで周囲の環境を認識し、自ら判断して動作することで、現実世界に直接働きかけることができます。その最前線にいるのが、人間のように動き、働くことができる「ヒューマノイドロボット」です。
米中の世界的企業によって、実用化が急速に進んでいます。物流倉庫での荷物運搬、製造現場での組立作業、さらには危険な環境での点検業務まで、人間が行ってきた様々な仕事を代替する技術として、産業界から大きな注目を集めています。
今回のセミナーでは、このフィジカルAI、特にヒューマノイドロボットの基礎から最新動向まで、体系的に学ぶことができます。
まずヒューマノイドの主な製品やAIについてご紹介します。 それぞれの製品の特徴を紹介することで、技術トレンドが見えてきます。
また、AIがどのように物理的な動作を実現しているのか、その仕組みにも触れていきます。
講師を務めるのは、株式会社想造技研の滝沢一博氏。豊富な知見と実務経験をもとに、技術的な側面だけでなく、実際の現場テスト事例、経験に基づくビジネスへの活用提案もご紹介します。活用提案を元に自社のビジネスへの応用可能性を具体的にイメージしていただくことも可能です。
ロボット工学の予備知識は一切不要です。これからフィジカルAI技術について学びたい方、自社での導入を検討されている方、新たなビジネスチャンスを探している方まで、幅広くご参加いただける内容となっています。
AIが情報の世界から飛び出し、人とともに働く未来は、もう目の前まで来ています。その最前線を、ぜひこの機会に体感してください。
聴講セミナー
2026年02月06日(金) 15:00-17:00
IoT技術が社会のあらゆる場面に広がる中、
開発現場では今、大きな変革が起きています。
その鍵となるのが、生成AIを活用した新しい開発手法「バイブコーディング」です。
従来のプログラミングは、構文やライブラリの知識を駆使し、
一行ずつコードを書き上げるのが当たり前でした。
しかし、生成AIの登場により、自然な言葉でAIと対話しながら、
アイデアを伝える感覚でプログラムを創り上げることが可能になっています。
今回のセミナーでは、このバイブコーディングをマイコン開発に適用する方法を解説します。
具体的には、Arduinoとセンサーを用いた事例を紹介しながら、
バイブコーディングの基本的な考え方から、
実際のマイコン開発における生成AI活用の最新動向まで体系的に学べます。
ChatGPTやClaudeなどの身近なAIツールを使い、
自然言語でマイコンやセンサーを制御するプログラムを生成する仕組みを理解し、
IoTシステムにおけるマイコン開発への適用方法を具体的に解説します。
センサーと連携するマイコンの開発やデバッグ作業も、
AIを活用すれば格段に効率化できます。
さらに、エッジAIとクラウドを組み合わせたスマートシステムの設計思想にも触れ、
これからの時代に求められる開発アプローチの全体像をつかんでいただけます。
本セミナーで学んだ知識は、
マイコンとセンサーを連携するIoTシステムの幅広い分野に応用可能です。
Arduinoとセンサーを活用したシステムは、温湿度やCO2濃度の自動記録、
熱中症対策のための気象データ収集、農業施設での環境モニタリングなど、
幅広い用途に対応できます。
これまでセンサーなど機器への知識不足で取り組めなかった課題にも挑戦できるチャンスです。
ご自身の業務や関心のある領域に、どう活かせるか。
そんな視点で受講いただくことで、具体的なサービス展開のヒントが見えてくるはずです。
プログラミング経験がない方も、どうぞご安心ください。
AIと対話しながら創る、これからの開発スタイルをぜひ一緒に体験してみませんか。
研究会
2026年02月05日(木) 15:00-17:00
XRが切り拓くビジネスの最前線と未来
生成AI技術の飛躍的な進化と高機能3Dソフトの普及により、
XR(VR/AR/MR)分野における3Dデータ活用は、
かつてないほど容易、かつ身近なものとなりました。
この技術革新は、単なるトレンドに留まらず、あらゆる業界の
サービス開発にパラダイムシフトをもたらし、
巨大なビジネスチャンスを生み出しています。
本研究会では、この歴史的な潮流を捉え、
「XR技術をいかにして具体的なビジネス成果に結びつけるか」を
テーマに掲げます。
ゲストには、「Society 5.0 × SDGs × Hero」という
独自のコンセプトを掲げてXR事業を牽引する、株式会社Meta Heroesの
北野氏をお招きします。
同社の先進的な事業展開やビジョンを伺いながら、
これからのXR産業が持つ可能性について、参加者の皆様と共に
深く掘り下げていきます。
PC実習型セミナー
2026年01月28日(水) 15:00-18:00
そのアイデアを今すぐ形に!ノーコード×生成AIでサービス開発体験
ビジネスや教育の現場で、いま注目されているのが、「ノーコード開発」と「生成AI」の組み合わせです。
これまで専門的な知識が必要だったアプリ開発も、ノーコードツールの登場によって、誰でも手軽に取り組めるようになってきました。
さらに、生成AIの活用により、情報の整理や提案といった高度な機能も、簡単にアプリに組み込めるようになっています。
今回のセミナーでは、スマートフォンで撮影した本の表紙やバーコードの画像から、情報を読み取って書籍の自動整理・管理できるアプリを作成します。
聴講セミナー
2026年01月28日(水) 15:00-17:30
共創のポイントを探るとともに、成果から見えてきた「5G」効果
5G X LAB OSAKA 連携企画
産業用途の通信規格であり産業の未来を担う「5G」。
通信キャリア(ソフトバンク)とメーカー(住友電工)が
共創により開発したプロダクトを通して、
その開発の裏側と共創の秘密をそれぞれの視点でお話します!
新たに開発されたプロダクトは「プライベート5G用端末( IGW5111 )」と言い、
工場や施設など限られた空間で最新の5G通信が使えるキャリア5Gと
ローカル5Gを掛け合わせたような製品です。
手軽にフルスペックの通信ができるところが特徴です。
本セミナーでは、この5G端末の共創事例について、両社の視点から
開発秘話や今後の展望などを解説。
共創の進め方やポイントなど聞きどころたっぷりです。
また、実際の「低遅延」や「大容量データ処理」を実現した
先進的な活用事例を通じて、開発側はもちろん、
導入側にとっても有益となる技術選定のポイントや、
実装ノウハウを伝授。5Gを活用することで業務やビジネスが
どのように変わるのかをお話しいただきます。
聴講セミナー
2026年01月23日(金) 14:00-16:30
運用改善から新規事業まで、通信×AIがもたらすビジネス変革の実践視点
IoTやAIが話題になる一方で、「通信技術がどう変わり、自社では何ができるのか」をまとめて学べる機会は多くありません。
急速に進化する通信インフラとAIは、いまや大企業だけでなく中堅・中小企業でも手の届く技術になりつつありますが、「どこから手をつけるべきか」「自社に合う使い方は何か」で立ち止まってしまうケースも少なくありません。
本セミナーでは、まず"5G/Beyond 5G"の基礎と、超高速・超低遅延・多数同時接続といった特性が現場のデータ活用にもたらすインパクトを、わかりやすく整理します。
そのうえで、AIによる画像解析やセンサー情報の即時処理を活かした、製造現場の検査自動化、物流倉庫の最適化、配送ルートのリアルタイム更新など、事例を交えて詳しく解説します。
現場の意思決定が、「勘と経験」から「データに基づく運用」へ変わるイメージをつかんでいただきます。
さらに、中堅・中小企業が無理なく始めるための導入ステップ、まず集めるべきデータのポイント、社内でDXを進める際の注意点など、明日からの検討に使えるヒントもお伝えします。
高速通信やAIを活用して、自社の新規事業やサービス改善につなげたい方におすすめのセミナーです。
皆さまのご参加、お待ちしております。
聴講セミナー
2025年12月19日(金) 14:00-16:15
AI×特許で事業化を推進!知財活用のポイントを分かりやすく解説!
生成AIを活用したビジネスに挑戦するかどうかは、
中小企業・スタートアップにとって大きなターニングポイントだと言えます。
ChatGPTの登場以来、生成AIは、
業務効率化はもちろん、新サービス創出の起爆剤となる等、
経営者や事業開発担当者の関心を集め続けています。
そうした「AI×新規事業」をテーマとしたセミナーは数多くありますが、
今回は「AI×特許」がテーマです。
「特許」は、早い・安いを実現する「生成AI」時代だからこそ必要な備えですが、
それ以上に、攻めの事業を推進するための強力な“武器”にもなるのです。
本セミナーでは、AIの知財戦略の専門家である弁理士の加島氏から
AIビジネスの『事業開発から特許取得まで』に焦点を当て、
戦略的な知財(特許)の活用方法をお話いただきます。
実際に特許取得支援も実施している弁理士が
事例も交えて情報提供します。
AI活用は、今からでも遅くありません。
ぜひ、皆様の事業をAIで飛躍させるヒントを
持ち帰ってください。
PC実習型セミナー
2025年12月17日(水) 13:00-17:00
MQTT×IoTで実現する次世代サービス開発の第一歩!
製造業や物流、建設など、さまざまな業界で注目されているのが、
センサーデータを活用した「IoTサービス」です。
これまで専門的な知識が必要だったIoTシステム開発も、
メッセージ駆動型プログラミングが簡単にできる「Node-RED」や、
軽量な通信プロトコル「MQTT」の登場によって、
効率的で拡張性の高いシステム構築が可能になってきました。
さらに、クラウドサービスとの連携により、最初は1台のデバイスから始めて
将来的には数千台規模の商用システムへと段階的に成長させることができる
設計手法が確立されています。
今回のセミナーでは、「転倒検知システム」を題材に、
センサーデータを収集し、リアルタイムで処理・通知する仕組みを実際に構築します。
開発に使用するのは、IoT分野で標準的に使われている通信規格「MQTT」と、
貸出用のRaspberry PiとNode-RED MCUを活用した開発環境、そして加速度センサーを搭載したESP32センサモジュール。
実習で使用したESP32センサモジュールは持ち帰ることができるので、
セミナー後も「Raspberry Piをご用意いただければ」ご自宅で動作確認や改造を続けることができます。
また、MQTTブローカーを介したデータ通信の仕組みを理解することで、
1台のデバイスで学んだ知識を、複数台へと展開していく際の
設計指針や拡張方法についても習得できます。
今回は「転倒検知」を題材にしていますが、ここで学ぶMQTTの仕組みや
センサーデータの扱い方は、あらゆるIoTサービスに共通する基本技術です。
設備の稼働監視、環境計測、物流トラッキング、品質管理など、
ご自身が携わる業界や業務にどう応用できるか、
そんな視点でご参加いただけると、より実践的な学びにつながります。
IoT開発が初めての方も大歓迎!
1台のデバイスから始める、
IoTサービス開発の第一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう!
聴講セミナー
2025年12月11日(木) 14:00-17:35
生成AIのアイデアが勢揃い!
新規ビジネスの挑戦者12組によるデモデイ開催!
いま、AIの進化は想像を超えるスピードで世界を変えています。
音声も、画像も、動画も自在に操る「統合型AI」の時代へと突入しています。
大阪産業局が主催する「TEQS Generative AI QUEST 2025」は、
この進化をビジネスに組み込むための
生成AI特化型アクセラレーションプログラムです。
約3か月間の厳しいブラッシュアップ期間を経て、
AIの社会実装を目指す精鋭12組の採択者たちが、ついにその成果を発表します!
さらに、今回は基調講演として、本プログラムのメンターであり、
AI分野の第一人者である遠藤 太一郎 氏と、南野 充則 氏にご登壇いただき、
本プログラムの振り返りに加え、
生成AIをはじめとする最新のビジネストピックについてもお話しいただきます。
生成AI活用のヒントが満載ですので、自社で活用される方はもちろん、
協業パートナーを探索される方にも必見の内容です!
聴講セミナー
2025年12月05日(金) 14:00-17:00
クリエイティブAIで、アイデアを即座にカタチへ!ビジネスを加速させる!
事業開発やサービス企画の現場で、いま急速に活用が広がっているのが「クリエイティブAI」です。
これまで外注やデザイナーへの依頼が必要だった画像、音楽、動画といった
クリエイティブ素材も、AIツールの進化により、誰でも短時間で高品質なものを作れるようになってきました。
今回のセミナーは、PCをお持ちいただき、実際に手を動かしながら学ぶトライアルセミナー形式です。
サービスコンセプトの説明動画、UI/UXモックアップ用の画像素材、
プレゼン用BGMなど、実際のビジネスシーンで必要となる素材を、その場で作りながら習得していきます。
アカウント作成から素材生成まで、講師と一緒にステップを踏んで進めていくので、初めての方でも安心してご参加いただけます。
こうした技術は、スタートアップや新規事業開発の現場で特に威力を発揮します。
投資家向けピッチに必要なプレゼン素材や、ユーザーインタビュー用のモックアップを素早く準備できれば、市場反応の検証サイクルを劇的に短縮できます。
リソースが限られる環境でこそ、このスキルは大きな武器になります。
セミナーの後半では、参加者同士でのディスカッションや質疑応答の時間も用意。
実際に作った作品を共有しながら、新しいサービス開発に取り組む方々との双方向の学びと知見共有の場となります。
今回習得する技術は、サービス紹介動画やブランド素材の制作だけでなく、SNSマーケティング、プレゼン資料の強化、社内コミュニケーションツールなど、幅広い用途への応用が可能です。
あなたのアイデアが、AIの力でカタチになる体験を、ぜひご一緒に!
Wi-Fi接続が可能なPC(Win、Macどちらでも可)をお持ちください。
各種AIのアカウント作成に、Googleアカウントが必要となります。
音楽生成の体験をされる方はイヤホンをお持ちください。
※聴講だけのご参加も可能です。